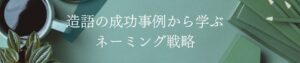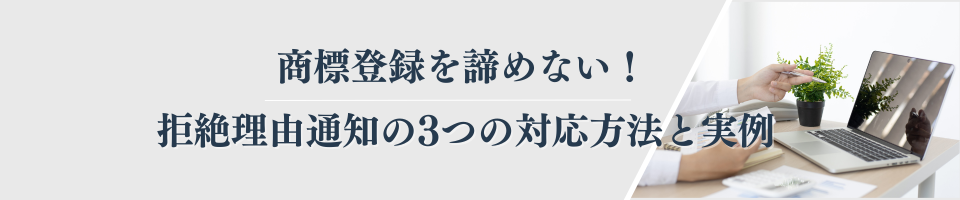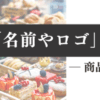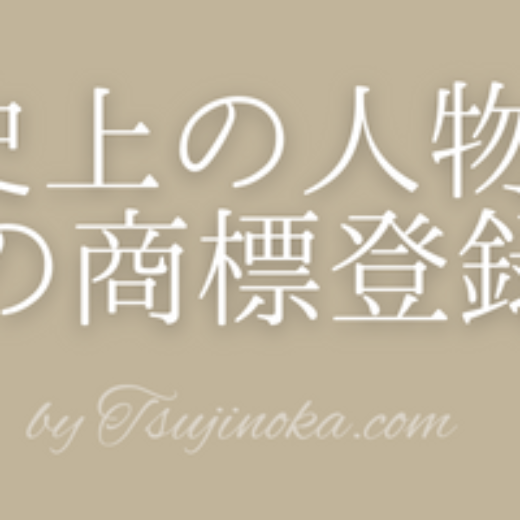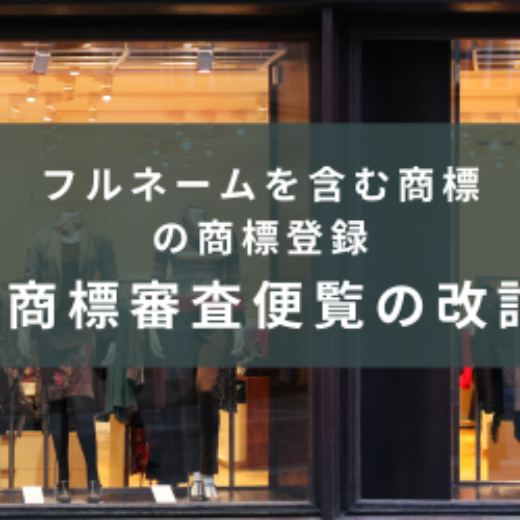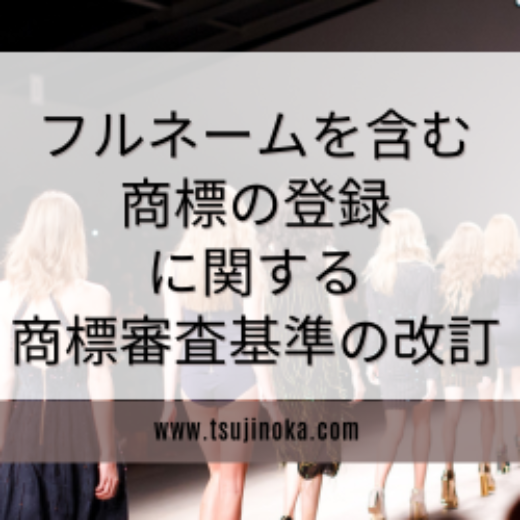はじめに
商標登録の出願をして、しばらく経つと特許庁から「拒絶理由通知」という書類が届くことがあります。
「拒絶理由」の文字を見て、「もう無理なのかな……」と落ち込んでしまう方も少なくありません。
でも実は、拒絶理由通知は「これから改善できるポイント」を教えてくれるお手紙のようなものです。
商標そのものを変更することはできませんが、意見書や補正を工夫することで登録につながるケースも多いのです。
この記事では、拒絶理由通知が届いたときの具体的な対応方法と、実際に私がサポートした事例をご紹介します。
1.拒絶理由通知のチェックポイント
拒絶理由通知は、「出願されたままでは登録できません」という特許庁の判断を伝える書類です。
これは「拒絶が決定した」という意味ではありません。
きちんと対応すれば拒絶理由が解消することも多いので、冷静に内容を理解して対応策を検討することが重要です。
(1)拒絶理由の内容を理解しよう
通知を受け取った段階で、出願人には意見を述べたり補正をする機会があります。
まずは慌てず、何が問題となっているのか、内容をしっかり読み解くことが大切です。
よくある拒絶理由には、次のようなものがあります:
- 似ている商標がすでに登録されている(類似している商標がある)
- 商品やサービスの説明にすぎない(識別力がない)
もし拒絶理由の内容に不明点などがある場合は担当審査官に電話やメールなどで確認することもできます。
※DX時代における商標審査官とのコミュニケーション/特許庁 shohyo_communication.pdf
(2)対応期限を確認しよう
拒絶理由通知には応答期限があります。
商標の場合、応答期限は拒絶理由通知の発送日から40日です。
「拒絶理由通知の発送日」、「応答期間」は拒絶理由通知書に記載されています。
(3)特許庁「商標の拒絶理由通知書を受け取った方へ」
特許庁のウェブサイトには、拒絶理由通知書を受け取った方のためのサポートページがあります。
拒絶理由通知書の見方、拒絶理由の解説が掲載されているほか、応答期限の計算もできますので、こちらをご覧になることをおすすめします。
商標の拒絶理由通知書を受け取った方へ | 経済産業省 特許庁
2.3つの対応策
基本的な3つの対応策をご紹介します。
(1)対応策その1:意見書や補正書を提出する
拒絶理由通知に対する主な対応策は、「意見書」や「補正書」の提出です。
これは、審査官が指摘した拒絶理由について説明や修正を行い、登録を目指すための手段です。
たとえば:
①拒絶理由「指定商品の記載が不明確である」なら
→指定商品の記載を明確なものに修正するための補正書を提出する。
②拒絶理由「他人が登録している商標と似ており、かつ、指定商品・指定役務も似ている」なら
→似ている指定商品・指定役務を削除するための補正書を提出する。
③拒絶理由「他人が登録している商標と似ており、かつ、指定商品・指定役務も似ている」であって、②の補正書に提出でも対応できないなら
→その登録商標と出願商標は似ていないことを説明する意見書を提出する。
④拒絶理由「自己の商品・役務と他人の商品・役務とを区別することができない商標」なら
→ 実際の商標の使用実績を示して、識別力があることを説明する意見書を提出する。
ただし、ここで注意が必要なのは、出願した「商標」を変更することはできない、という点です。
補正で修正できるのは、指定商品・指定役務の記載に限られます。
商標のデザインや文字などの要素を追加したい場合は、新しい商標として別途出願する必要があります。
(2)対応策その2:別の商標を検討する
意見書や補正書で対応するのが難しい場合は、「別の商標を新たに出願する」という選択肢もあります。
ブランドイメージを損なわない範囲で、文字のレイアウトやデザインを工夫したり、別の視点から考えたネーミングを新たな商標とすることで、登録できる可能性が高まります。
私はこうした「代替案」をご提案するお手伝いもしています。
(3)対応策その3:専門家に相談する
拒絶理由通知の対応においては、登録商標と出願商標はどの指定商品・指定役務で類似しているのか、どうやって登録商標と出願商標は似ていないことを説明するのか、など専門的な観点が必要となる場面もあります。
そのため、専門家に相談して戦略を練ることで、より効果的な対応ができます。
弁理士は、過去の審査の傾向や事例を踏まえたアドバイスができるのが強みです。
「まだ可能性はあるのか」「どんな補正や説明が有効か」など、ぜひ遠慮なくご相談ください。
3.実際のサポート事例
事例1:新たな商標で再チャレンジして登録できたケース
お客様ご自身で出願手続をしたところ他人の登録商標に類似するとの理由で拒絶されてしまったが、大切なブランドなので再チャレンジしたいというご相談があり、商標の文字のレイアウトデザインを変更して再チャレンジしたところ、無事登録されました。
事例2:識別力がないと指摘されたケース
ありふれた表現だとして拒絶理由が出ましたが、実際の使用実績や販売状況を資料として提出することで、識別力があると認められました。
4.まとめ:拒絶理由通知は「改善のチャンス」
拒絶理由通知は決して「終わりのお知らせ」ではありません。
意見書や補正書で対応できるケースは多く、場合によっては別案を検討することで道が開けます。
諦める前に、ぜひ一度ご相談ください。
お問い合わせはこちら
あなたの大切な商標が無事に花開くよう、全力でサポートします。
拒絶理由通知が届いてお困りの方は、ぜひお気軽にご連絡ください。
↓こちらもどうぞ!