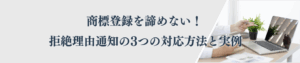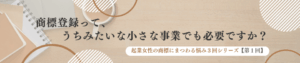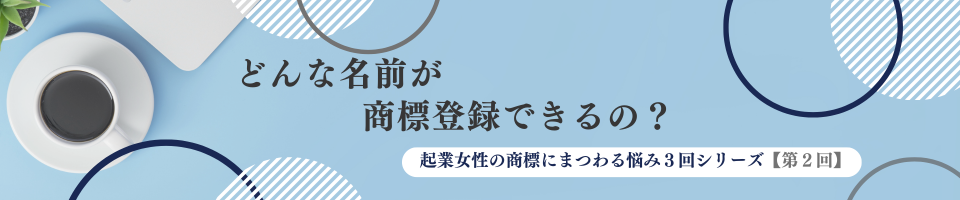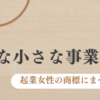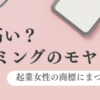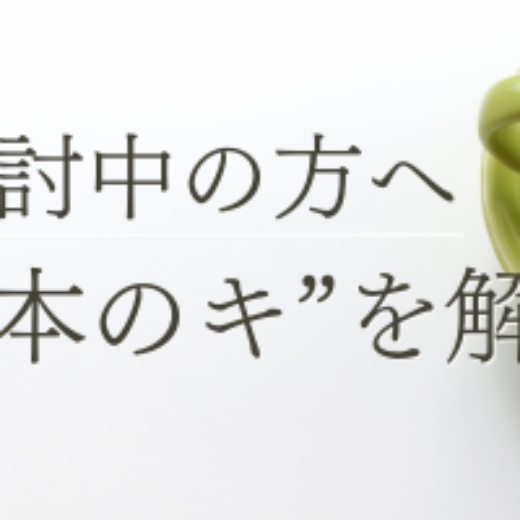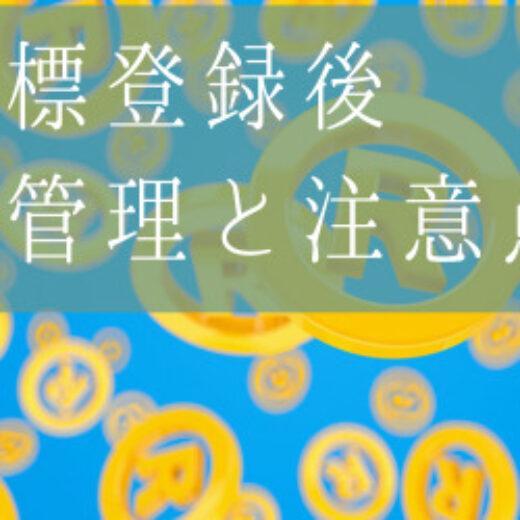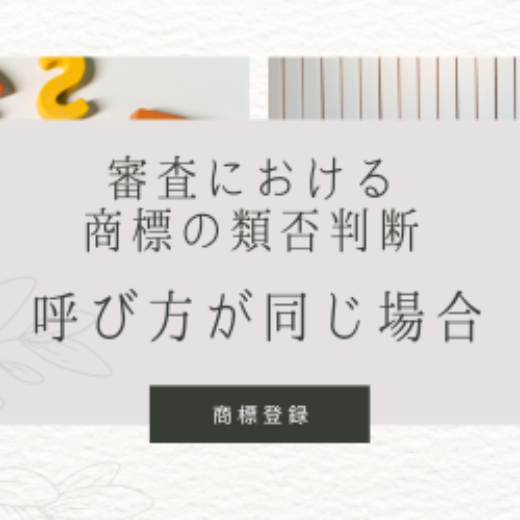起業女性の商標にまつわる悩み3回シリーズ【第2回】

「ネーミングが決まったけど、これって登録できるの?」
最近もこんなご相談をいただきました。
「ブランド名が決まりました!でも調べたら、似たような名前があって…これって登録できるのか不安で…」と。
ブランドの名前は、事業への想いやコンセプトが詰まった大切な存在ですよね。
でも、商標登録できるかどうかを知らずに進めてしまうと、せっかくの名前をあとから変更しなければならないこともあります。
今回は、そんな悩みにお答えして、
- どんな名前が登録できるのか
- 商標調査のコツ
- ネーミングを考えるときのポイント
を、わかりやすく解説していきます。
登録できるかどうかには、2つの重要な視点があります
商標登録の可否を判断するポイントは、大きく次の2つです:
① 他に似た名前がすでに登録されていないか
→ すでに登録されている商標と「似ている」と判断されると、登録はできません。
② 名前が単なる説明になっていないか
→ 一般的な言葉や、商品の特徴を表す言葉だけでは登録できません。
実はこの「説明的な名前」、多くの方が無意識に選んでしまいがちなんです。
① 登録できるかどうかは「似ているかどうか」がポイント
審査では、「登録されている商標と似ていないか?」がチェックされます。
このとき、以下の3つの点から商標が似ているかどうかが判断されます:
- 呼び方(称呼):読み方が似ているかどうか
- 見た目(外観):文字やロゴの形が似ているか
- 意味(観念):文字やロゴから生じる意味が似ているか
たとえば、
- 「セレリティ」と「セレニティ」は音が似ている
- 「緑の丘」と「みどりのおか」は呼び方が同じ
など、読み方が同じだと、商標同士が似ていると判断される傾向にあります。
② 説明的な名前は、登録が難しい
もう一つ大切なのが、「名前が商品・サービスの説明になっていないか?」という視点です。
例としては:
- 「おいしいパン」や「北海道とうもろこし」
- 「天然素材の石けん」や「こだわり野菜の店」
このように、それを目にした人が、誰かの商品・サービスの目印として認識できないような言葉は、商標登録が認められにくいのです。
起業された方からはよく、
「わかりやすい名前にしたいから…」
「商品の良さが一目で伝わるように…」
という理由で説明的な名前を選ばれることがありますが、実はこの「わかりやすさ」が、商標登録の壁になることもあるのです。
商標調査のコツ:自分でざっくり確認するには?
特許庁の「商標検索サイト(J-PlatPat)」を使えば、誰でも商標の登録状況を確認できます。
👉 J-PlatPat(商標検索ページ)
調べたい名前を検索してみて、同じ名前や似たような名前が見つかったら要注意です。
特におすすめなのが、「称呼(しょうこ)検索」。
これは、“読み方が同じ”商標を調べられる機能で、たとえば「みどりのおか」「緑の丘」など表記が違っても読みが同じ商標を見つけることができます。
表記が違っても呼び方(称呼)が同じだと、似ている商標と判断されて拒絶されるケースが多いので、この「称呼検索」で調べることは有効です。
ただし、検索結果をどう判断するかは難しい場合も多いため、「出てこなかった=登録できる」とは限らない点にもご注意ください。
商標登録を意識したネーミングのコツ3選
説明にならないように注意する
→ 一般的な特徴や成分だけの名前は避ける
造語・組み合わせで個性を出す
→ 例:「SONY」、「アスクル」のように、意味を込めつつ他にない言葉に
音・リズム・見た目の印象を大切に
→ 似た名前が多そうなジャンルでは、特に「音の違い」が勝負
不安なときは専門家に相談を
ネーミングの段階でご相談いただければ、調査しながら一緒に名前を考えることもできます。
「いざ出願してみたら、似た名前があって登録できなかった…」というリスクを避けられます。
実は、「登録できる名前を前提に考える」ことが、事業の安心感につながるんです。
✨まとめ
商標登録では「似ていないこと」と「説明になっていないこと」が大切
ネーミングは「オリジナリティ」+「伝えたい思い」を込めて
J-PlatPatでざっくり検索。不安があれば専門家へ。
次回予告
第3回は、「商標登録って高い?費用とタイミングのモヤモヤを解消」をテーマに、登録にかかるコストや、出願のベストなタイミングについて詳しくお話しします。
↓こちらもどうぞ